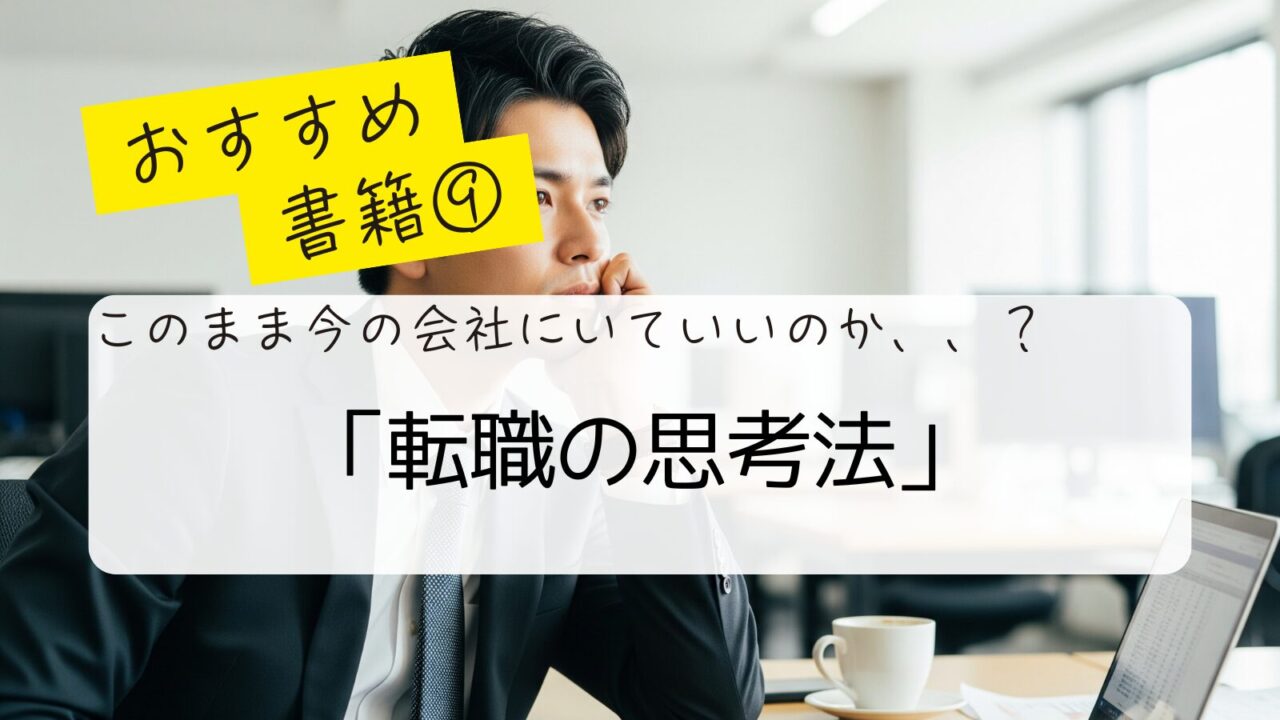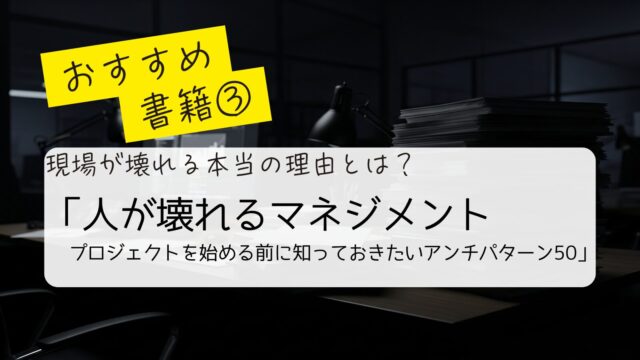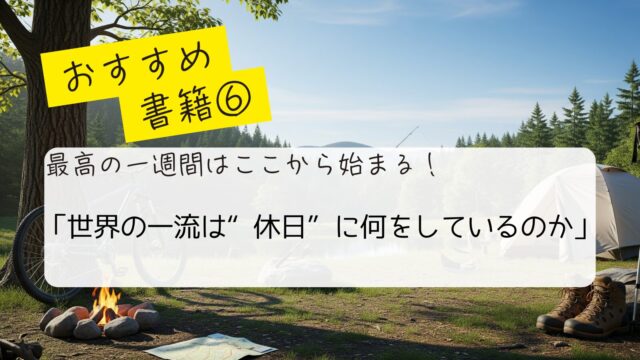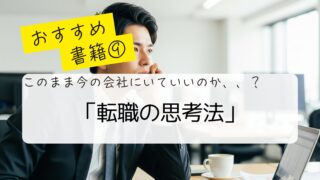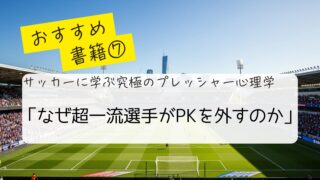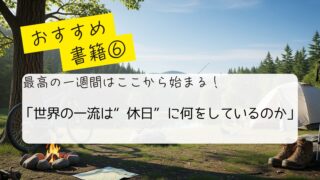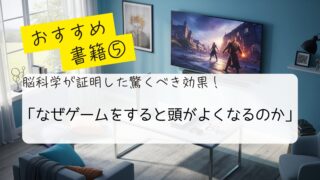転職は「逃げ」ではない──キャリアを設計するための第一歩
現代を生きる多くのビジネスパーソンにとって、「このまま今の会社にいていいのだろうか?」という漠然とした不安は、常に心のどこかにある問いではないだろうか。終身雇用神話が崩壊し、企業の寿命が短くなる中で、私たち個人のキャリアもまた、変化への対応が求められる時代になった。そんな中で、「転職」という選択肢が頭をよぎることもあるだろう。しかし、「転職は逃げなのでは?」「もっと頑張るべきなのでは?」といった躊躇や、「給料が下がるのは嫌だ」といった具体的な不安に直面し、なかなか一歩を踏み出せない人も少なくないはずである。
北野唯我氏の著書『転職の思考法』は、まさにそんな私たちの根源的な問いに対し、情報ではなく「思考法」という羅針盤を与えてくれる一冊である。本書の核心は、「転職は単なる努力の放棄ではない。受け身で会社を選ぶという発想ではなく、自ら市場価値を考えていく。転職とは自分を大きく成長させる機会である」と述べられている点である。これは、転職という行為を単なる職場探しと捉えるのではなく、自身のキャリアを能動的に設計し、自身の市場価値を高める戦略的な手段として位置づけるべきだという、著者の強いメッセージだと私は解釈している。
あなたの市場価値を構成する3つの要素とは?
私が本書を読んで最も腹落ちしたのは、個人の「市場価値」という概念の解像度が格段に上がったことである。漠然と「市場価値」という言葉は使っていたが、それを構成する要素が具体的に言語化されていることに感銘を受けた。北野氏は、この市場価値を以下の3つの要素の掛け算で説明している。
- 技術資産(テクニカルアセット): 「何ができるのか」というスキルや専門知識。これは、まさに私たちの仕事における「武器」と呼べるものだ。特定のプログラミング言語の熟練度、データ分析能力、マーケティング戦略立案能力など、その仕事でしか通用しないニッチなスキルもあれば、汎用性の高いポータブルスキルもある。重要なのは、そのスキルがどれだけ希少で、どれだけ高い生産性につながるかということである。例えば、ChatGPTのようなAIツールが進化する中で、単なる情報収集や定型業務のスキルは陳腐化しやすい一方で、AIを使いこなして新しい価値を生み出すスキルはより価値を持つようになるだろう。自分の持つ技術資産が、どのくらいの「賞味期限」と「希少性」を持っているのか、常に問い続ける必要があると痛感した。
- 人的資産(ヒューマンアセット): 「誰とでも組めるか」「誰にでも好かれるか」という人脈や信頼関係。これは、ともすれば「コネ」といったネガティブなイメージを持たれがちだが、本書が言う「人的資産」は、もっと本質的な信頼関係構築能力を指していると理解している。単に知り合いが多いということではなく、困難な状況で助け合える仲間がいるか、新しいプロジェクトを立ち上げる際に協力してくれる人がいるか、といった「共創」の礎となるものだ。特に、20代では目に見えるスキルである技術資産が重視されやすい一方で、30代、40代と経験を重ねるにつれて、この人的資産の重要性が増していくという指摘は非常に納得感があった。どれほど優れた技術を持っていても、それを活かすための信頼関係がなければ、真価を発揮することはできない。人と人との繋がりが生み出す価値の大きさを改めて認識させられた。
- 業界の生産性(インダストリープロダクティビティ): その業界に属する個人が平均してどれだけの価値を生み出しているかを示す指標。これは個人の努力では変えにくい要素であり、いわば「パイの大きさ」である。私自身、以前は「個人の努力さえあれば、どんな業界でも成功できる」と考えていた時期があった。しかし、本書を読み、その考えが甘かったと反省した。
(前略) 技術資産も人的資産もない人が会社を選ぶ際は実質二択だ。ひとつは①生産性がすでに高い産業。もうひとつは②エスカレーターが上を向いている産業だ。
北野 唯我. このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法 (p.47). ダイヤモンド社. Kindle 版.
という言葉は、私たち個人のキャリアに与える業界の影響の大きさを端的に示している。例えば、かつて隆盛を誇った産業でも、時代の流れとともに衰退していくことは珍しくない。そこでいくら個人が努力しても、全体のパイが縮小していれば、給与や昇進の機会は頭打ちになる可能性が高いのである。自身のキャリアを考える上で、今いる業界、あるいはこれから飛び込もうとしている業界が、果たしてどの方向に向かう「エスカレーター」に乗っているのかを冷静に見極める視点は、非常に重要だと感じた。
この3つの要素をかけ合わせるという考え方は、自分のキャリアを客観的に評価するための強力なフレームワークになる。自身の強みはどこで、弱みはどこか、そしてそれは市場においてどのように評価されるのか。これらを具体的に言語化することで、漠然とした不安が具体的な課題へと変わり、対策を講じられるようになるのだ。
仕事にも寿命がある──ライフサイクルで読み解くキャリアの落とし穴
本書で提示されるもう一つの重要な視点は、仕事の「ライフサイクル」という概念である。私たち人間と同じように、仕事にも「寿命」があり、生まれては消滅していくという考え方は、ある意味で残酷だが、非常に現実的だ。北野氏は、仕事のライフサイクルを以下の4つの段階で説明している。
- ニッチ(Niche): 新たな価値が生まれ、競争相手が少なく、高い付加価値を生み出せる段階である。
- スター(Star): 成長期に入り、競争が激化する段階である。
- ルーティンワーク(Routine Work): 仕事が標準化され、誰でもできる作業が増える段階である。
- 消滅(Decline): 仕事が自動化されたり、市場から完全に需要がなくなったりする段階である。
これは、プロダクトのライフサイクル論を仕事に当てはめたもので、非常に分かりやすい比喩だと感じた。特に、ルーティンワークの段階に突入した仕事の危険性については、深く考えさせられる。多くの企業は、効率化のために仕事を標準化し、誰でもできるようにシステム化しようとする。これは企業にとっては合理的な行動だが、その仕事に従事する個人にとっては、専門性や付加価値が低下し、最終的には代替されやすいというリスクにつながる。AIやRPAの進化により、この「ルーティンワーク」の範囲はますます広がり、かつては専門的とされていた仕事の一部も、自動化の波に飲まれつつある。
・すべての仕事は、ライフサイクルに沿って生まれては消えていく
・会社は、すべての仕事をシステム化し、代替可能にしようとする
・自分の仕事が①(ニッチ)ならエスカレーターは上向き、③(ルーティンワーク)なら下向き
北野 唯我. このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法 (p.55). ダイヤモンド社. Kindle 版.
という言葉は、私たちへの警告だと受け止めるべきだろう。自分の今の仕事がライフサイクルのどの段階にあるのか、そして将来的にどの方向に向かっているのかを冷静に見極めること。そして、もしルーティンワーク化が進んでいたり、消滅の兆候が見えるのであれば、早めに次のステージを模索する準備を始めることの重要性を強く訴えかけている。これは
いまのままじゃいけない気がするけど、転職して給料が下がるのも嫌……
北野 唯我. このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法 (p.4). ダイヤモンド社. Kindle 版.
という漠然とした不安を解消するためにも不可欠な視点だと、私は確信している。
転職を成功に導く4つの「思考の型」とは
本書は、転職を単なる「行動」ではなく「思考」の連続として捉え、具体的な4つのステップを提示している。これは、闇雲に求人情報を探すのではなく、体系的にキャリアを構築するための強力なフレームワークである。
- STEP 1: 自分の市場環境を測り、高める: これは前述した「技術資産」「人的資産」「業界の生産性」を客観的に評価するフェーズである。自分の強みや弱みを正確に把握し、自分が市場でどんな価値を提供できるのかを明確にする。これは、転職活動以前に、私たち自身が自分のキャリアを棚卸しする上で非常に有効な自己分析ツールとなる。
- STEP 2: 今仕事の「寿命」を測る: 現在の仕事がライフサイクルのどの段階にあるのかを判断するステップである。この客観的な視点を持つことで、現状維持のリスクを具体的に認識し、今後のキャリアプランを立てる上での重要な判断材料となる。たとえ今が安定しているように見えても、将来的なリスクを予測し、備えることの重要性を教えてくれる。
- STEP 3: 「僕のやりたかったこと」に、伸びる市場にコミットする: ここが非常に重要なポイントだと感じた。単に「やりたいこと」だけを追求するのではなく、それが市場で高く評価され、成長が見込める分野であるかを重視する、という視点である。自分自身の才能やスキルがたとえ突出していなくても、身を置く市場を選ぶことで、その価値を最大限に引き出すことができる。自分の情熱と市場のニーズが交差する点を見つけ出すこと。これが、充実したキャリアを築く上での鍵だと私は考えている。
- STEP 4: ベストな会社を見極める: 最後のステップは、単に「有名企業だから」とか「大手だから」といった表面的な理由で会社を選ぶのではなく、自身の「働くべき」仕事と「本当にやりたいこと」が両立できる企業を見極めることである。自分が貢献できる領域(働くべき仕事)と、自身の情熱や興味(本当にやりたいこと)が一致し、さらに企業の文化や風土が自分に合致する場所こそが、「ベストな会社」であるという認識は、私も強く共感する。
「働くべきこと」と「やりたいこと」のバランスが人生を変える
本書がキャリアを考える上で最も重要視しているのが、この「働くべき」仕事と「本当にやりたいこと」のバランスである。
「働くべき」仕事とは、市場から高く評価され、結果として高い報酬や安定が得られる仕事である。これは、自分の市場価値を高め、社会から必要とされるスキルや経験を身につけることを意味する。一方で、「本当にやりたいこと」とは、個人の内発的な動機に基づき、心から楽しんで取り組める仕事である。趣味の延長線上にあることや、長年の夢である場合もある。
この二つが両立している状態、すなわち「緊張と調和のバランス」が取れている状態こそが、理想的な仕事だと本書は定義している。常に挑戦を求められ(緊張)、同時に自身の成長と達成感を得られる(調和)ことで、仕事への意欲が持続し、結果としてパフォーマンスも向上する、という考え方だ。
私自身も、これまで仕事を選ぶ際に「好きかどうか」を最優先していたが、それが必ずしも長期的なキャリアの充実につながるとは限らないという現実に直面することもあった。この「働くべきこと」という視点を取り入れることで、より広い視野で仕事の選択ができるようになったと感じている。
結論:転職に必要なのは情報ではなく、思考の武器である
結論として、『転職の思考法』は、単に次の職場を探すという行為ではなく、自身のキャリアを戦略的に設計し、主体的に市場価値を高めていくための哲学と具体的なステップを提供するものである。この本は転職市場に関する情報を提供するのではなく、
転職に必要なのは、情報ではなく「思考法」である
北野 唯我. このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む 転職の思考法 (p.22). ダイヤモンド社. Kindle 版.
というメッセージが示す通り、読者自身が変化の激しい時代を生き抜くための普遍的な「思考の型」を身につけることを支援している。
私たちはとかく、転職サイトの情報を漁ったり、成功者の体験談を参考にしたりすることに終始しがちである。もちろんそれらも無意味ではないが、本当に重要なのは、自分自身がどのような市場価値を持ち、どのようなキャリアを築きたいのかという「軸」を持つことである。本書が提供してくれるのは、その「軸」を自らの手で見つけ、磨き上げるための「思考の武器」なのだ。
自身の市場価値を正確に把握し、仕事のライフサイクルを見極め、そして自身の「働くべき」仕事と「本当にやりたいこと」が両立する環境を見つけることで、多くの人が抱えるキャリアの「もやもや」を解消し、心から納得できる充実したキャリアを築くことができるだろう。この思考法を実践することで、あなたは転職は「怖い」ものではなく、躍進するための新たな可能性であると認識できるようになるはずだ。
もし、あなたが今、キャリアに対する漠然とした不安を抱えているのであれば、ぜひ一度、この『転職の思考法』を手に取ってみることを強くお勧めする。それはきっと、あなたのキャリアに対する認識を根底から覆し、新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれるはずだ。