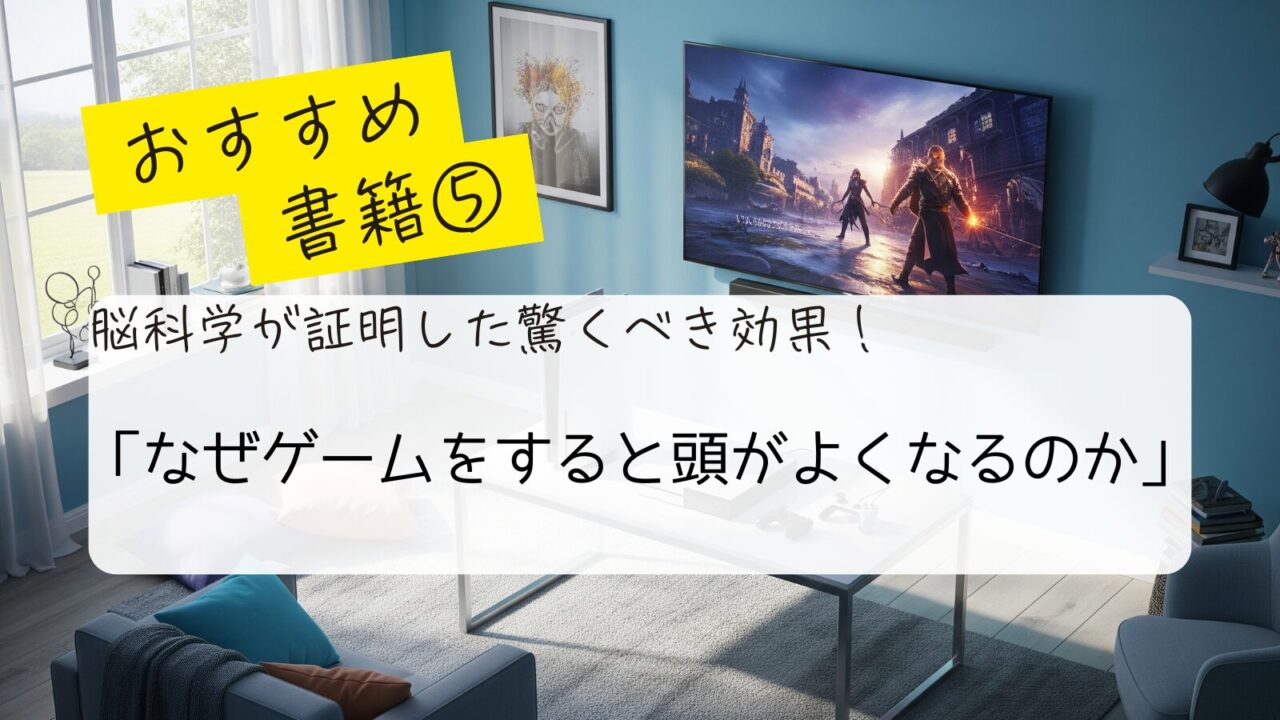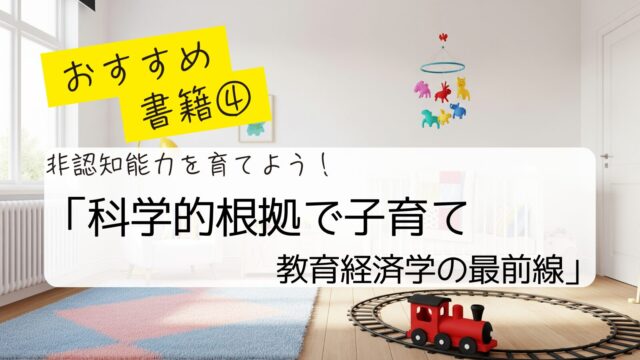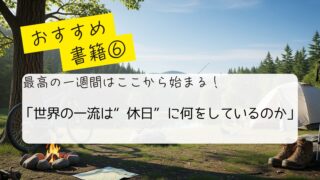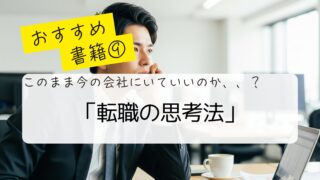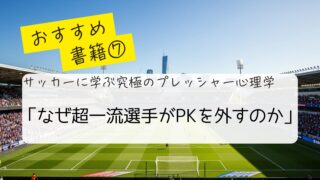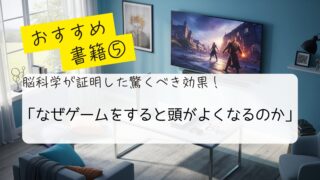「ゲーム=悪」の時代は終わった。脳を鍛え、教育・医療・ビジネスに応用される“賢いゲーム活用”の新常識とは?
私は、これまでゲームに対して少なからず偏見を抱いていた。テレビやニュースで耳にするのは、ゲーム依存症の問題や、ゲームが学業の妨げになるという話ばかりであった。私自身、子供の頃にゲームに夢中になりすぎて親に叱られた経験もあるし、周りの大人たちも「ゲームは悪」という共通認識を持っていたように思う。しかし、今回『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』という書籍を読み、その固定観念がいかに根拠のないものだったかを痛感した。本書は、最新の脳科学や研究に基づいた科学的な視点から、ゲームの持つ計り知れない潜在能力と、それと適切に付き合う方法を教えてくれる、まさに現代社会の必読書である。ゲームをプレイする人、その家族、そして教育者やビジネスパーソン、さらには健康に意識の高いすべての人にとって、この本は「目から鱗が落ちる」体験となるだろう。
脳科学が明かす!ゲームで認知能力が向上する理由とは
正直なところ、この本を手に取るまでは、ゲームが脳に良い影響を与えるなどとは夢にも思っていなかった。せいぜい反射神経が少し良くなる程度、というのが私の認識であった。しかし、本書を読み進める中で、ゲームが私たちの脳に物理的な変化をもたらし、それによって認知能力が向上するという事実に、私は大きな衝撃を受けた。
私たちの認知能力は、脳のさまざまな部位や機能によるものですが、ゲームをすることで、実際に脳が変化して、それにより、認知能力が上がるということがわかってきているのです。
たとえば、ゲームをすることで、短期記憶の役割を果たす海馬の灰白質が増大したり、ワーキングメモリーを支える前頭葉(背外側前頭前野)が拡大、活性化することが報告されています。もちろん、手先などの筋肉を動かす小脳も同様に拡大、活性化することも知られています。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (pp.18-19). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
これはまるで、体を鍛えれば筋肉がつき、より高いパフォーマンスを発揮できるようになるのと同じではないだろうか。ゲームをすることで、私たちの脳は文字通り鍛えられ、その結果として記憶力や集中力、判断力といった幅広い認知スキルが向上するというのは、私にとって全く新しい発見であった。
シューティングゲームやアクションゲームは、空間認識能力と注意力を高めてくれるということです。ゲームをすることで、意識できる視野が広がり、目の前で起こる変化をより正確に把握できるようになり、視覚情報の処理スピードがアップする。さらに、注目すべき対象に焦点を当てて、無関係の出来事に惑わされない集中力がアップする。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (pp.33-34). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
まさにゲームは認知能力アップのトレーニングの役割をしてくれているのです。そしてさらに極め付き!空間認識能力やワーキングメモリー、短期記憶を良くすることは、理系の力を伸ばすことに直結します。前述の例にもあるように、数字を意識して、足し算を実践したり、図形や実験を観察したり、道具や機械装置の操作を覚えて実践したり。空間や形を認識する能力や、目の前にあるものに注目したり、意識したりする力、さらには、いったん意識したものを思い出す力。これらの能力は理系のスキルには欠かせません。つまり、ゲームは、理系の力を訓練してくれる効果的なツールなのです。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.35). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
これまでの私のゲームに対する認識が、いかに時代遅れで偏ったものだったかを痛感させられた。ゲームが単なる娯楽の域を超え、私たちの学習能力や問題解決能力を飛躍的に向上させる可能性を秘めていると知ったことは、私にとって大きな希望となった。
そして、ゲームの持つ医療的な側面もまた、非常に驚くべき点であった。アメリカの政府機関であるFDA(食品医薬品局)が、ゲームを医療機器として認証しているというのだ。
(前略) そのVR空間の中でプレーできる、「Zengence」(ゼンジェンス)というゲームがあります。攻め寄せてくるお化けを魔法ビームでやっつける、いわゆる「FPS」(ファーストパーソン・シューティングゲーム)で、魔法ビームのコントロールを自分の呼吸や声で調整していくのが特徴のゲームです。 (中略) VRのゲームでもあるにもかかわらず、アメリカの連邦機関であるFDAに高血圧の治療法として認可されたからです。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.3). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
正直言って、目を疑った。薬物治療ではなく、ゲームが治療に用いられるなんて、想像もしていなかったからである。特に、
最初のシリアス・ゲームとしてのFDA認可は、2020年に、ADHDの治療法として開発された「EndeavorRx」(エンンデバー・アールエックス)というゲームでした。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.27). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
という事実は、ゲームの医療応用が単なる夢物語ではなく、すでに現実のものとなっていることを雄弁に物語っている。これは、ゲームが、薬物治療では得られない、あるいは薬物治療と組み合わせることでより効果的な治療法を提供する可能性を秘めていることを示唆しており、今後の医療分野におけるゲームの役割に大きな期待を抱かせる。まさかゲームが、私たち人間の健康を支える重要なツールとなり得るとは、本書を読むまで全く思いもしなかった内容である。
ゲームは本当に悪か?暴力・依存症に関する科学的検証
私たちの社会では長年、「ゲームは悪」という見方が根強く存在していた。特に、私が子供の頃には、ゲームがしばしば「諸悪の根源」や「依存症の温床」として槍玉に挙げられていたことをよく覚えている。1999年のコロンバイン高校銃乱射事件以降、「ゲームが暴力を助長する」という見方が社会に広く浸透し、そのイメージは私の中に深く刻み込まれていた。しかし、本書はこれらの「都市伝説」を科学的に検証し、その誤解を解き放ってくれる。
たとえば、2000年代にはすでに、ゲームと暴力には相関がないことを示す論文が発表されていました。ゲームと暴力の関係性について研究した論文を数多く集めて、全ての結果をがっちゃんこ総合的にゲームと暴力の関係を評価するメタ分析を行ったところ、ゲームと暴力に有意な相関性が見られなかったという報告が出てきていました。
加えて決定的だったのが、論文出版のバイアスです。当時の世の中の見方がすでにゲームを悪者にする論調に傾いていたため、論文誌に掲載される論文も、そうした世論に合致した結果を示したものに傾きがちだったのです。実際に、そうした論文出版のバイアスを取り除くと、これまでの論文のデータからは、ゲームと暴力の有意な関係を見出すことができなくなります。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.52). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
でも一つはっきりしているのは、「ゲームが暴力の原因だ!」とか、「ゲームと暴力は全く関係ない!」といえるほど、ゲームと暴力の関係は単純ではないということです。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.53). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
長年ゲームにまつわる議論の根底にあったこの誤解に、決定的な終止符を打つものだ。私が学生時代に友人とゲームを楽しんでいた際、親や教師から「ゲームばかりしていると暴力的になる」と言われ、漠然と罪悪感を抱いていたことがあったが、今になって思えば、それは科学的根拠に基づかない単なる偏見であったと理解できる。ゲームと現実の暴力の関連性を安易に結びつけるのではなく、それぞれの問題を個別にかつ多角的に分析することの重要性を改めて認識させられたし、この事実をもっと多くの人に知ってほしいと強く感じる。
また、WHOが「ゲーム障害」を認定したことで、ゲーム依存症への懸念はますます高まっている。しかし本書は、「ゲーム依存症の原因はやりすぎではない」と大胆に主張する。この主張には、正直驚きを隠せなかった。多くの人が抱いている「ゲームを長時間プレイすることが依存症の原因」という認識とは、あまりにもかけ離れているからだ。本書が指摘するように、ゲーム障害になりやすい人の特徴は、現実世界で孤独だったり、自己肯定感が低かったり、周りからのプレッシャーの中でいつもいなければいけない人といったいうように、心理的欲求が満たされていないことにあるというのだ。私自身、過去に何かから逃避したい、あるいは現実世界で満たされない欲求を抱えていた時期に、特定の趣味に過度に没頭しすぎた経験がある。ゲームもまた、その「根本的な欲求」を満たすための手段の一つに過ぎないのかもしれない、と本書を読んで深く納得した。
ゲームの中で問題を解決したり、難関ステージをクリアすることで、達成感や有能感、つまり、現実の世界で感じられていない「できる感」を得ることができるわけです。ですがやはり、いったんその感覚を感じても、ゲームをやめた途端、学校や仕事場の現実に戻らなくてはいけない。そこではやはり「できる感」を感じられない。それゆえに、満たされない「できる感」を求めて、ゲームに依存していってしまうのです。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.74). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
ゲームが単なる娯楽ではなく、人間の根源的な心理的欲求と深く結びついている可能性を示唆している。この視点は、ゲーム依存症へのアプローチを根本から変える可能性を秘めていると感じたし、問題の根本を見つめることの重要性を改めて教えてくれる。
そして、ゲームとの健全な付き合い方を考える上で欠かせないのが、適度なプレイ時間の重要性だ。本書は、
ゲームはやりすぎはいけないが、やりすぎない人がいい!
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.66). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
と、非常にシンプルかつ的確なメッセージを伝えている。何事も「過ぎたるは及ばざるがごとし」という言葉があるように、ゲームも例外ではない。研究によると、1日1〜3時間のプレイが最も学業成績や認知能力に良い影響を与えるというデータは、私たちに具体的な指針を与えてくれる。長時間プレイによるパフォーマンス低下や依存症のリスクが増加するという事実は、単にゲームを禁止するのではなく、適切な時間管理とバランス感覚を養うことの重要性を強調している。特に、幼い子供を持つ親にとっては、0~5歳の幼児に推奨される1日1~2時間以内というプレイ時間の目安や、監督下での教育的なゲームプレイの重要性といった具体的なアドバイスは、非常に実践的で有益だと感じたし、もっと早く知りたかった情報である。
ゲームとの健全な付き合い方:脳を鍛え、依存を防ぐ方法
本書は、単にゲームの良い面を羅列するだけでなく、ゲームとの賢い付き合い方についても具体的な方法を提案している。この実践的なアドバイスこそが、本書の最も価値ある部分だと私は感じた。
まず、「ゲーム禁止」は避けるべきだという提言には強く共感した。これまでゲームを頭ごなしに否定し、禁止する家庭や学校を多く見てきたが、それは根本的な問題を解決せず、むしろ子供たちの好奇心や自律性を奪う結果に繋がりかねない。重要なのは、ゲームと健康的な関係を築くための「バランス感覚」を育むことだ。これは、親や教育者が子供たちと共に考えるべき課題であり、一方的に禁止するだけでは何も解決しないと、改めて認識させられた。
そして、ゲームが満たしている心理的欲求を、現実世界で満たす代替活動を見つけるというアプローチは、非常に建設的だと感じた。もし、ゲームに過度にのめり込んでしまう人がいるならば、それは単に意志が弱いからではなく、現実世界で「つながり」「やればできる感」「自主性」といった根源的な欲求が満たされていないからかもしれない。そうであるならば、オンラインコミュニティへの参加、新しいスキルの学習、ボランティア活動、友人との交流など、現実世界でこれらの欲求を満たす機会を増やすことが、結果的にゲームとの健全な距離を保つことに繋がるだろう。これはゲーム依存症の治療だけでなく、誰もがより充実した生活を送るための普遍的なアドバイスとして受け止めることができるし、私たち自身のライフスタイルを見直す良いきっかけにもなる。
さらに、本書が提示するゲーム時間の「科学的な減らし方」も、非常に実践的だ。単に「時間を減らせ」と言うのではなく、2時間で15分程度の休憩を挟むといった具体的な時間の区切り方は、私たちが日々の生活の中でゲーム時間を管理する上で非常に役立つだろう。漠然と「ゲーム時間を減らそう」と思うだけでは難しいものだが、具体的な方法論が示されていることで、実践へのハードルが大きく下がると感じた。また、「友とのコラボが最高のゲームプレイ」という点は、ゲームが単なる個人的な娯楽ではなく、コミュニケーション能力や協調性を育む社会的なツールとしての側面も持つことを示唆している。対戦ゲームでも「フロー」状態に入ることでストレス解消になるという点は、ゲームが精神的な健康にも寄与する可能性を示しており、興味深い洞察である。私自身、オンラインゲームを通じて新しい友人ができた経験があり、ゲームが現実の人間関係にも良い影響を与えることを実感している。
そして、ゲームを通じて「やればできる」という「成長マインドセット」を育むという考え方には、深く感銘を受けた。ゲームの世界では、努力すれば必ず結果に繋がるという経験を繰り返し得ることができる。この経験は、現実世界で困難に直面したときにも、「諦めずに挑戦すれば乗り越えられる」という前向きな姿勢を育むことに繋がる。これは、学業や仕事、人間関係など、人生のあらゆる側面において私たちを強く支える力となるだろうし、子供たちの教育にも積極的に取り入れたい考え方だと強く思った。
教育・医療・ビジネスで注目される「シリアス・ゲーム」の力
本書の後半で紹介される「シリアス・ゲーム」の概念は、ゲームが単なる娯楽の枠を超え、いかに社会に大きな影響を与え始めているかを教えてくれる。この章は、ゲームの未来を考える上で非常に重要な示唆を与えてくれるものであった。
本章で取り上げるシリアス・ゲームは、(中略) ゲーム自体で授業や仕事の目的を達成しようというのがシリアス・ゲームです。
星 友啓. なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) (p.26). 株式会社PHP研究所. Kindle 版.
単に授業や仕事にゲームの要素を導入する「ゲーミフィケーション」とは異なる点が特徴である。
「Minecraft」が教育ツールとして活用され、創造的思考や問題解決能力を育んでいるという事例や、企業が社員研修やマーケティングにシリアス・ゲームを取り入れ、従業員のモチベーション向上やブランドイメージの強化に繋げているという話は、ゲームの持つ計り知れない可能性を私たちに示してくれる。もはやゲームは子供の遊びではなく、社会を動かす大きな力となりつつあるのだ。そして、前述したADHD治療の「EndeavorRx」に代表されるように、医療分野におけるシリアス・ゲームの発展は、まさに革命的と呼べるだろう。これらの事例は、ゲームが持つエンターテインメントとしての側面だけでなく、問題解決や学習促進、さらには治療といった、より高度な目的を達成するための強力なツールとなり得ることを明確に示している。
ゲームが私たちを強く動機づける理由は、目標達成感や自己決定権といった内発的動機付けを提供できることにあると本書は分析している。私自身も、夢中になってゲームをプレイしていて、ふと気づくと何時間も経っていた、という経験がよくある。それはまさに、ゲームが持つ内発的動機付けの力が強く働いているからだと深く納得した。この内発的動機付けの力を、教育や医療、ビジネスといった分野に応用することで、私たちはこれまで解決が困難だった社会課題に、新たなアプローチで挑むことができるようになるはずだ。ゲームが、私たちの社会をより良くするための強力な武器となり得ることに、私は大きな期待を抱いている。
ゲームと脳科学の未来:豊かな人生を築くための新常識
『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』は、ゲームに対する私のこれまでの認識を根底から揺さぶる、非常に示唆に富んだ一冊であった。この本を読む前は、ゲームは単なる時間の浪費であり、場合によっては有害なものだとさえ考えていた。しかし、本書は、これまで私たちが「悪」と決めつけてきたゲームが、実は脳の認知機能向上、精神状態の改善、さらには医療や教育、ビジネスといった多岐にわたる分野でポジティブな影響をもたらす可能性を秘めていることを、科学的な根拠に基づいて明確に示している。これは、私たちの社会がこれまで見過ごしてきた、ゲームの持つ計り知れない価値を再発見する機会を与えてくれたと心から感じている。
本書が提唱する「ゲーム禁止」ではなく、「バランス感覚を養う」というアプローチは、現代社会においてゲームと賢く付き合っていく上で非常に重要だと感じた。ゲームが提供する「つながり」「やればできる感」「自主性」といった心理的欲求を理解し、現実世界でもそれらを満たす代替活動を見つけること。そして、適切なプレイ時間を守り、成長マインドセットを育むこと。これらは、ゲームを単なる娯楽としてではなく、私たちの成長を促し、人生を豊かにするための強力なツールとして活用するための具体的な指針を与えてくれる。この視点を持つことで、私たちはゲームを一方的に排除するのではなく、むしろ積極的に、かつ賢く生活に取り入れていくことができるようになるだろう。
この本を読み終えて、私はゲームに対する見方が180度変わった。もはやゲームは、非難されるべきものではなく、むしろ現代社会を生き抜く上で不可欠な、そして非常に強力な「脳のトレーニングツール」であり、「心の栄養剤」であると確信した。教育関係者、親御さん、そしてゲームをプレイするすべての人に、ぜひ一度手にとって読んでほしい一冊である。この書籍が、ゲームを巡る不毛な議論に終止符を打ち、ゲームが持つ真の可能性を最大限に引き出すための建設的な対話が始まるきっかけとなることを願っている。
あなたにとって、ゲームはどのような存在だろうか? この本を読んだ後、その答えが変わるかもしれない。もし、少しでもゲームに対する認識を変えたいと思っているのなら、ぜひこの本を読んでみてほしい。新たな発見と、より豊かな未来へのヒントがきっと見つかるはずだ。
▼この本から得られる学び(まとめ)
- ゲームは脳を物理的に鍛える「トレーニング」である
- 暴力や依存との因果関係は科学的に否定されている
- ADHD治療など医療分野での活用が進んでいる
- ゲームは心理的欲求を満たす重要な手段
- 健全なプレイ習慣が学力・集中力・成長マインドセットを育む
- 教育・企業・医療で社会を変える「シリアス・ゲーム」の力