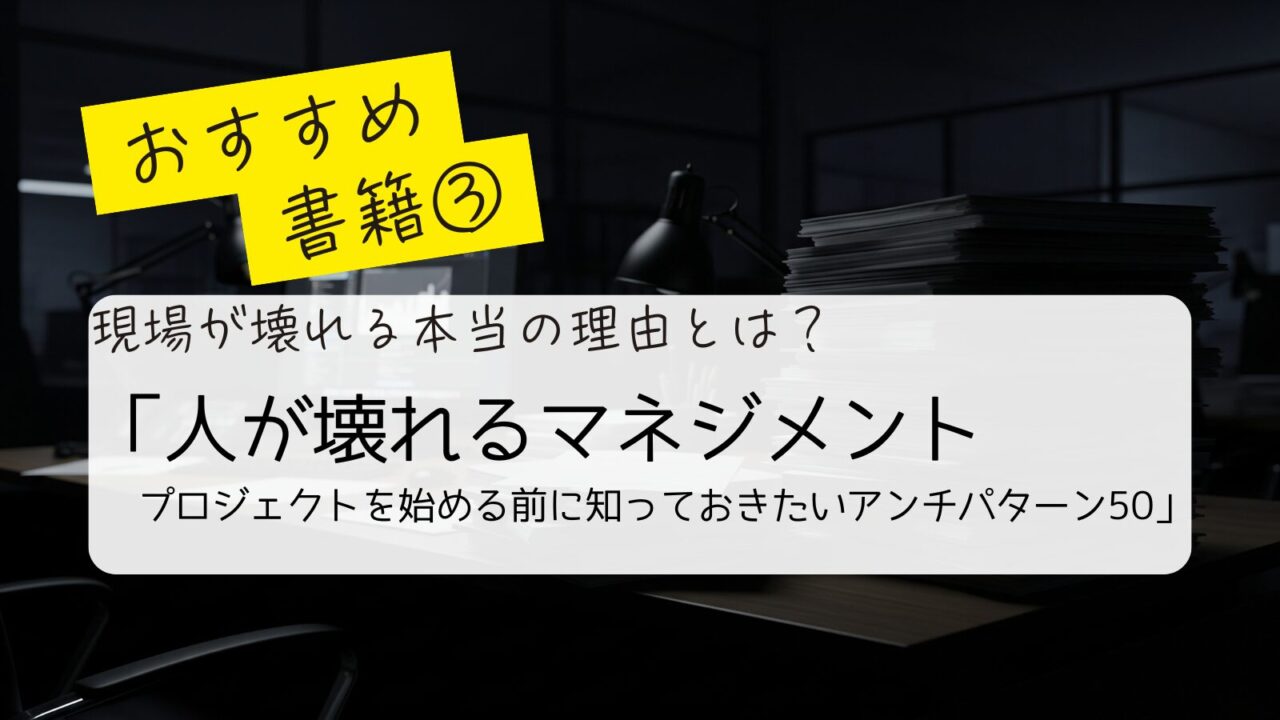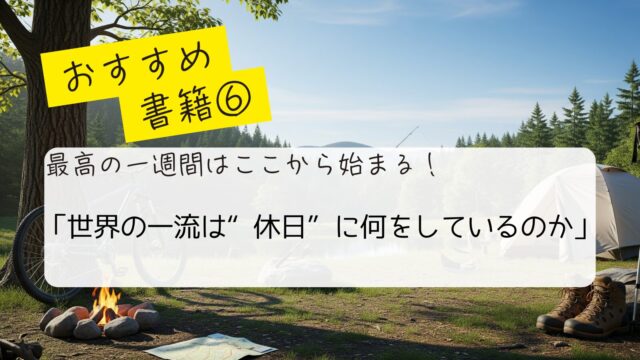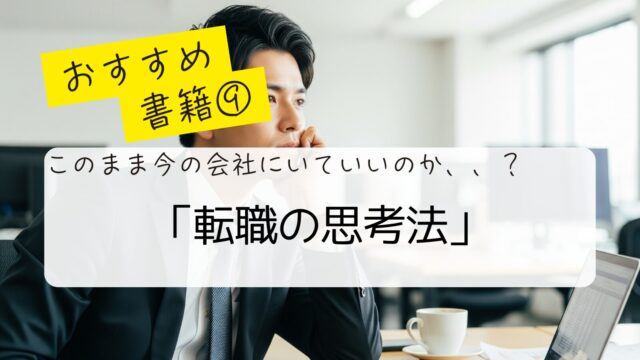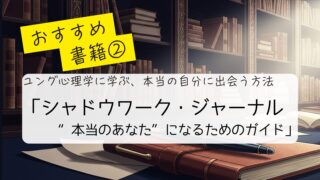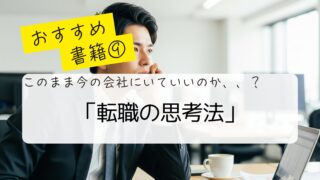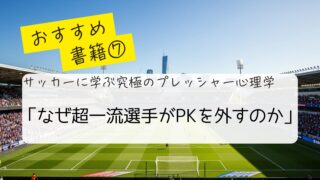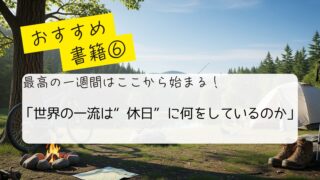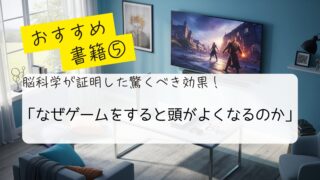「部下をどう育てればいいか分からない」「マネジメントが以前より格段に難しくなった」と感じているマネージャーは、私だけではないはずである。少子高齢化による人手不足が深刻化し、多くの企業が「人財」の有効な活用方法を見つけられずにもがき続けているのが現状だ。
本書が冒頭で警鐘を鳴らすように、
プロジェクトは成功すれば業務効率を向上させたり、大きな売上を立てたりすることができますが、失敗すれば事業面・人材面で非常に大きなデメリットが生じます。このデメリットの中で最大のものは「人を壊す」ことです。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 54/2869]。
この一文を読んだとき、私は背筋が凍る思いがした。単なる業務遂行の失敗に留まらず、個人の心身に深い傷を残し、最終的には組織全体の持続可能性を脅かすという本書の主張には、深く頷かざるを得ない。
本書は、このような「致命的なミス」を回避し、健全なマネジメントを確立するための実践的なアンチパターンと、その具体的な対策を提示している。本稿では、私が特に現代のビジネスパーソンにとって重要だと感じたアンチパターンを厳選し、そこから得られる示唆について考察していく。
タスク管理が壊す職場:丸投げ指示と長時間労働の危険性
プロジェクトの土台となるのは、日々のタスク管理である。しかし、この最も基本的な部分にこそ、人を壊すアンチパターンが潜んでいると本書は鋭く指摘している。これは、多くの組織が見落としがちな盲点であり、日々の業務の積み重ねが、気づかないうちに人々に深い疲弊をもたらしていることに警鐘を鳴らしている。
まず、
普段のプロジェクトの現場で最もよく見るマネジメントの失敗事例は「タスクの丸投げ」です。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 176/2869]。
というアンチパターンは、正直、多くの組織で日常的に経験されていることだろう。私自身も、過去に目的も背景も不明確なままタスクを振られ、途方もない不安と「なぜ自分がこれをやるのか」という不信感を感じた経験がある。
目的、内容、担当者、場所、期限、方法、量といった6W2Hが不明確なままタスクが与えられる状況は、担当者に深い不安と不信感を与える。これは、単なる「指示不足」という言葉では片付けられない、マネージャー側の「責任転嫁」に近いと感じている。なぜなら、真に仕事を「任せる」のであれば、前提条件や期待する成果、さらにはサポート体制まで明確に伝えるのがマネージャーの責務だからである。
漠然とした指示は、担当者の自律性を育むどころか、逆に自主性を奪い、思考停止を招きかねない。結果的に、成果物の品質が低下し、何よりも担当者のモチベーションが著しく損なわれるという悪循環に陥るのである。
さらに深刻なのは、
(前略) プロジェクトの実行体制が確保されていない企業では、ほとんど日常茶飯事といえるほど炎上が常態化しているケースもあります。こうした組織では残業や持ち帰り仕事、休日出勤が頻繁に行われ、それが「異常なこと」であるという認識すらないことがあります。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 288/2869]。
という現代社会が抱える根深い問題である。「炎上は百害あって一利なし」と本書は断言する。
私が危惧しているのは、「残業している人が頑張っている」「残業しない人はやる気がない」という誤った評価基準が依然として根強く残っている企業があることである。このような文化が蔓延している限り、真の生産性向上は望めない。
タフさを誇る文化があるということは、適切なマネジメントが行われていない証拠でもあります。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 305/2869]。
という指摘は、多くの日本の企業にとって、耳が痛い現実を突きつけているのではないだろうか。
このような状況を改善するには、単に「早く帰れ」と言うだけでは不十分である。根本的なプロジェクト計画の見直し、具体的なタスクの優先順位付け、そして時には「やらないこと」を決める勇気ある決断がマネージャーには求められる。働く人の健康と幸福を犠牲にして得た成果は、決して持続可能ではない。
プロジェクト計画の失敗パターン:現場を壊すスケジュールと要件不明のリスク
プロジェクトの成功は、その計画の精度に大きく左右されるが、ここにも人を壊す落とし穴が数多く存在する。私が強く感じるのは、計画の不備は、単なる見通しの甘さだけでなく、しばしば経営層の不適切な意思決定や、現場への過度な期待が背景にあるということである。
非現実的な締め切りを設定されて壊れるというアンチパターンは、多くのプロジェクトで共通して見られる問題であり、私自身も幾度となくこの状況に直面してきた。
上層部が現実を顧みずに設定する締め切りは、現場を「形だけ」のスケジュールで動かすことになり、結果的に
通常の見積りによってスケジュールを立てていれば無理なく進められたプロジェクトでも、願望による非現実的なスケジュールによってミスやトラブルが頻発したため数倍の時間がかかってしまう、(後略)
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 567/2869]。
という、皮肉な結果を招く。
これは、現場の人間がどれだけ努力しても、物理的に不可能である場合が多く、最終的には個人の責任として処理されがちだが、根本原因は経営層の計画性の甘さにあると強く感じる。健全なプロジェクト運営には、必要な工数を積み上げ、20~50%程度のバッファを見込んだ現実的なスケジュール作成が不可欠である。
さらに深刻なのは、
決まっていない要件や仕様を元にタスクを進めさせられて壊れる
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 613/2869]。
という状況である。本書はDXを例に挙げており、
たとえば、DXとして業務を効率化するために業務システムを開発する場合、現状の業務ががどうなっているかの調査や必要なシステムの検討など、実際のシステムを開発するために必要な検討事項はかなりの量に上ります。 (中略) こうした状況で往々にして起こるのが、とりあえず着手できる作業から始めるという「見切り発車」です。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 613/2869]。
とある。
この「とりあえず」という思考停止が、どれだけの時間とコスト、そして「人」を消耗させているかを、経営層はもっと真剣に考えるべきである。曖昧な要件で走り出すことは、霧の中を地図なしで進むようなものであり、事故の元でしかない。
コミュニケーション不足が招く孤立:信頼関係なき組織の末路
プロジェクトを動かす「血液」と本書が表現するように、コミュニケーションはチームや組織の活性化に不可欠である。特にリモートワークが普及した現代において、その重要性は以前にも増して高まっていると痛感している。
コミュニケーションの不足で壊れるというアンチパターンにおいて、プロジェクトに必要なコミュニケーションが欠けていると、
たとえば、課題や不安を共有する場がない場合、メンバーは「自分だけが問題を抱えている」と感じ、孤立感を抱くことがあります。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 1454/2869]。
とあり、また、
プロジェクトではポジションに応じた公平な負担感がなければ信頼関係が崩壊してしまいますが、甘えは「断れない人」に一方的に負担をかけやすくしてしまい、最終的にその人を潰してしまうことにもつながります。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 1454/2869]。
とある。
孤独感は、生産性の低下だけでなく、精神的な健康問題にも直結する深刻な課題である。また、「孤独感」や「甘え」を引き起こさないために重要なのは、仲の良さと信頼関係の違いを理解することである。単に仲が良いだけでは、仕事上の課題や本音を話し合う信頼関係には繋がらない。
マネージャーは、意識的に「対話の機会」を作り出し、メンバー一人ひとりが孤立していないか、常にアンテナを張るべきである。このような仕事として必要なコミュニケーションに配慮することは、心の健康を保ち、チームワークを醸成する上で不可欠だと確信している。
キャリアパス不在が若手を壊す:成長できない組織の共通点とは
個人のキャリアパスは、プロジェクトの成功と組織の持続性に直結する重要な要素である。現代の若手社員は、かつてのような「会社に人生を預ける」という意識は薄れ、自身のスキルアップやキャリア形成に高い関心を持っている。
キャリアパスの不明確さで壊れるというアンチパターンは、特に若い世代の離職に大きく影響している。
しかし、ビジネスのグローバル化や終身雇用制の崩壊、さらに業務やプロジェクトの専門性の高度化や働き方の価値観の多様化によって、従来のキャリアパスのあり方が通用しなくなっています。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 2038/2869]。
という本書の指摘は、まさに現代社会の実情を表している。
もし明確なキャリアパスが提示されなければ、社員は自身の将来に不安を感じ、「このままで良いのか」という疑問を抱き、より魅力的なキャリア機会を求めて他社へ転職してしまうのは当然の流れである。
キャリアパスは、会社が一方的に示すものではなく、社員一人ひとりの希望や適性に合わせて共に「創り上げていく」ものという認識を持つべきである。社員が自律的にキャリアを考え、会社がそれをサポートする関係性こそが、これからの時代に求められる。
人を壊す組織文化:無意味な組織変更と社内政治の弊害
プロジェクトを成功させるには、個人のマネジメントだけでなく、組織全体の文化や環境を健全に保つことが不可欠である。これらの問題は、往々にして現場レベルでは解決しきれず、経営層の強いコミットメントと意識改革が求められる領域だと本書は教えてくれる。
無意味な組織変更で壊れるというアンチパターンは、多くの組織が陥りがちな問題であり、私自身も目的が不明確な組織変更に戸惑った経験がある。
組織変更は競争環境や事業戦略の見直しに応じて必要不可欠だが、
しかし、組織変更が無計画であったり、合理的な理由が不明確であったりすると、労働者の混乱や不信感を招き、結果として組織全体のパフォーマンスを低下させる要因となります。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 2393/2869]。
と本書は指摘する。
正しいマネジメントとして、
変更の背景や意図を、中長期の事業戦略を元に経営陣や管理職だけでなく現場の社員や顧客に十分に説明し、「なぜこの変更が必要なのか」「どのようなメリットがあるのか」を明確に説明します。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 2434/2869]。
このように組織変更の目的を明確にすることで、混乱を防ぎ、社員や顧客双方にとってプラスとなる組織変更を実施する必要がある。
社内政治で壊れるというアンチパターンは、組織が肥大化するにつれて顕在化する、非常に根深く、そして疲弊させられる問題である。
社内政治が現場の社員に与える最大の問題は、「実力よりも人間関係が重視される環境の形成」です。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 2459/2869]。
は、
社員が努力し、スキルを磨き、成果を出しても、評価が「上司や派閥との関係」によって左右されるようになると、組織への信頼を失います。
橋本将功『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』Kindle版、ソシム、2025年、[位置No. 2461/2869]。
という致命的な状況を生み出す。
これは、頑張る意欲を根こそぎ奪い去り、優秀な人材が育たなくなるだけでなく、最終的には組織全体の腐敗に繋がりかねない。透明性と公平性を徹底し、パフォーマンスが正当に評価される環境こそが、社員のモチベーションを維持し、組織を強くする唯一の道だと信じている。
人を壊さないマネジメントとは?持続可能な組織運営のための実践提言
本書『人が壊れるマネジメント』は、プロジェクトマネジメントにおける多岐にわたる「アンチパターン」を明確にし、それらがいかに組織や個人に深刻なダメージを与えるかを具体的に示している。そして、それぞれの問題に対して、より健全で効果的なマネジメント方法を提案することで、持続可能な組織運営と人材育成を支援しようとする意図が強く感じられる。
現代の複雑な社会において、企業が成長し続けるためには、プロジェクトを成功させるだけでなく、そこで働く「人」を大切にすることが不可欠である。本書は、そのための具体的な羅針盤となるだろう。机上の空論ではなく、現場で実際に起こりうる問題を的確に捉え、具体的な解決策を提示している点が、この本の最大の魅力だと思う。
マネージャーだけでなく、プロジェクトに関わる全ての人が本書を手に取り、自身のマネジメントや働き方を見つめ直すきっかけとなることを強く勧める。この一冊が、多くの組織で「人が壊れる」状況を食い止め、より健康的で生産性の高い職場環境を築く一助となることを強く期待している。
私たちは、未来の労働環境をより良いものにするために、本書から多くの学びを得て実践していく責任があると感じている。一人の人間が壊れることで失われるものは計り知れない。私たちは、そうした悲劇を二度と繰り返してはならないのである。
あなたの組織では、これらのアンチパターンにどのように対処しているだろうか?